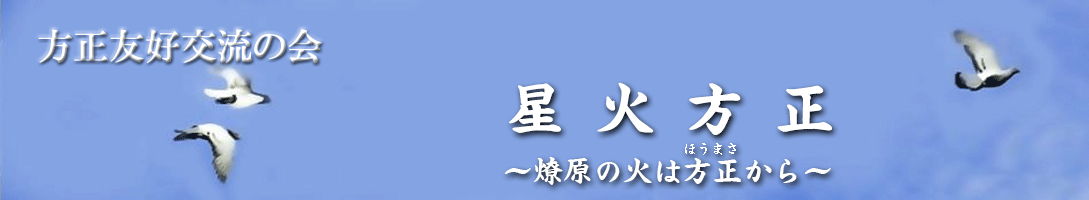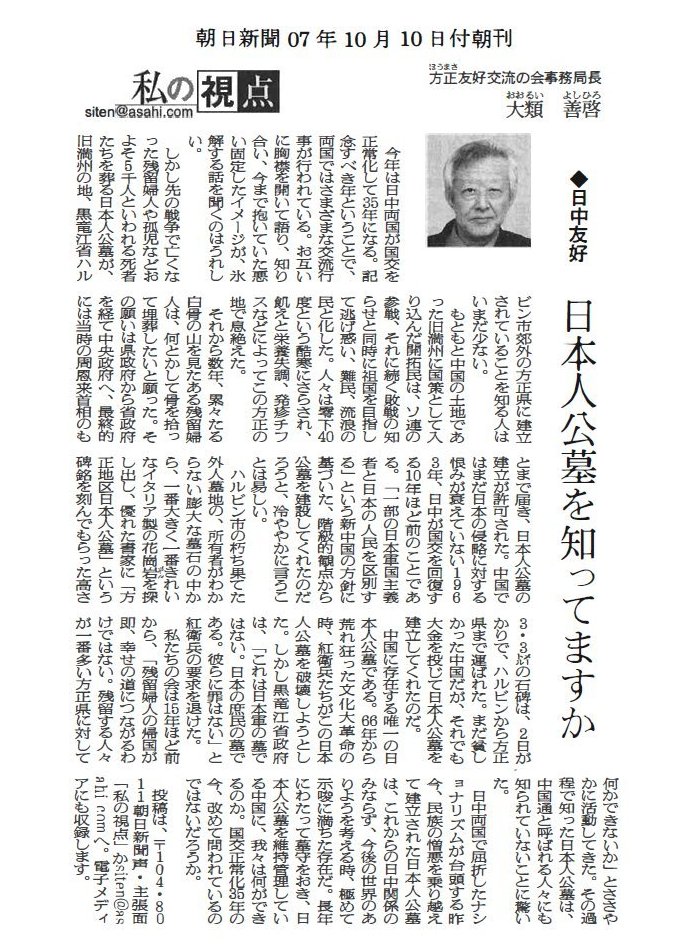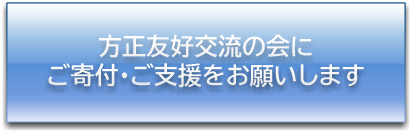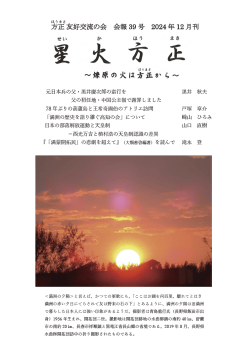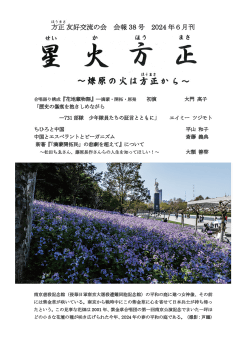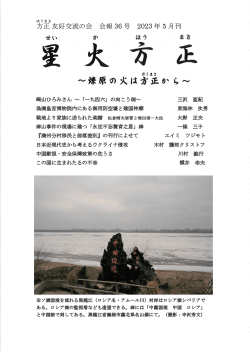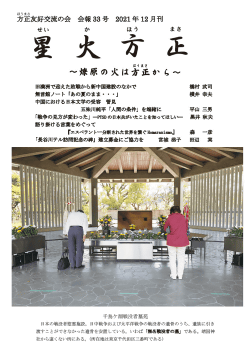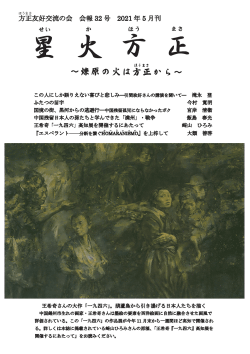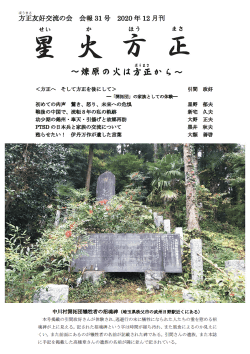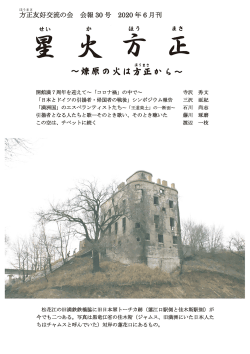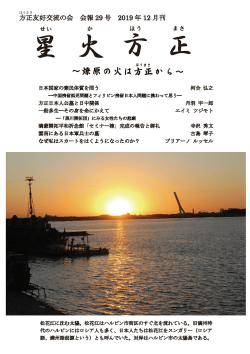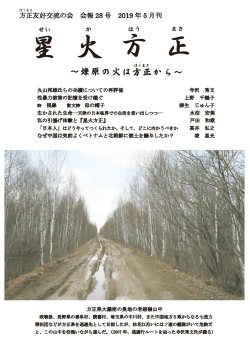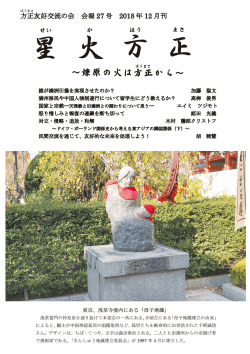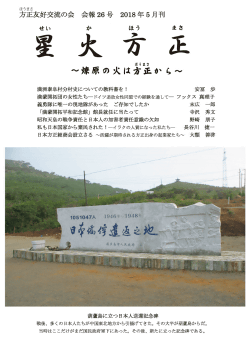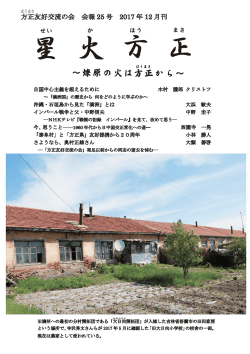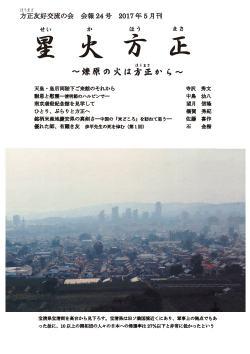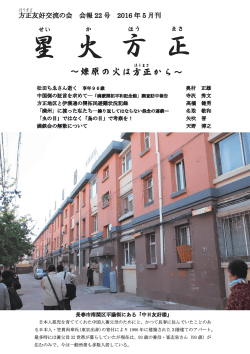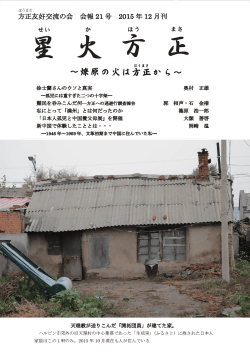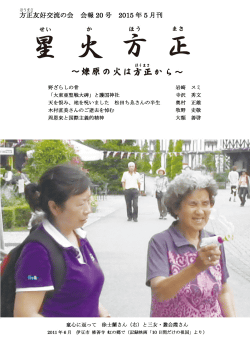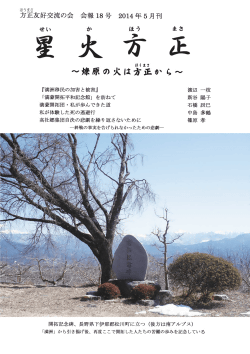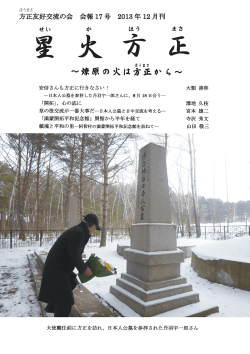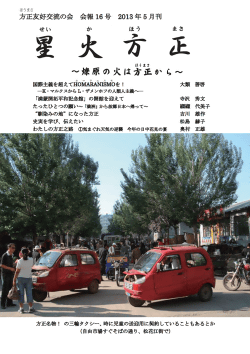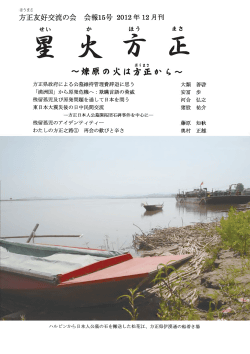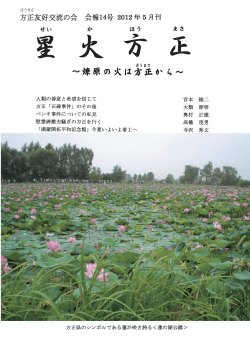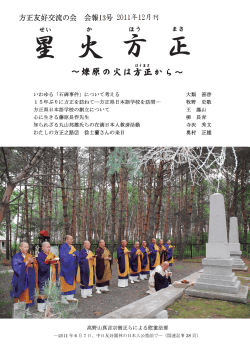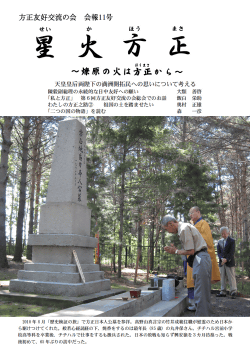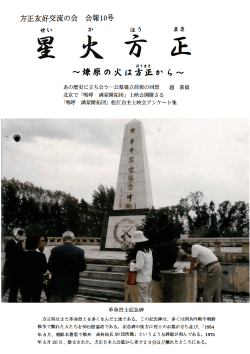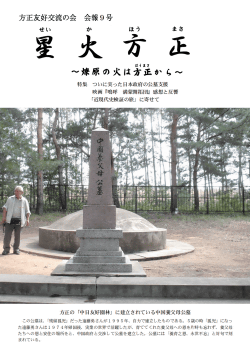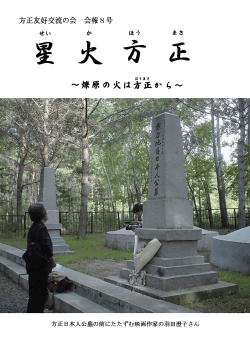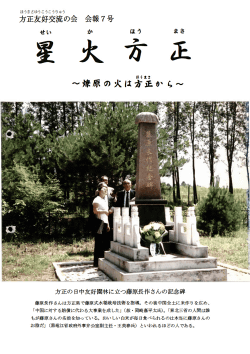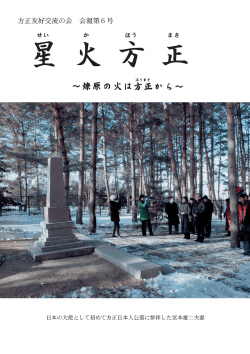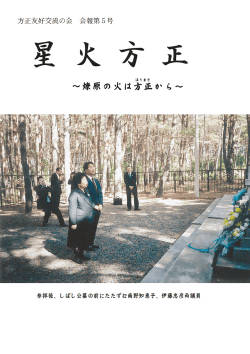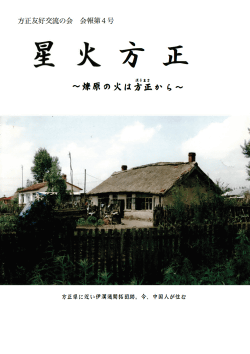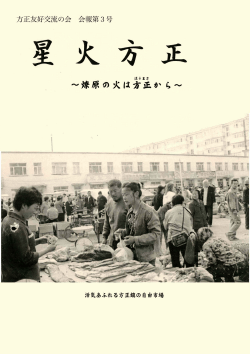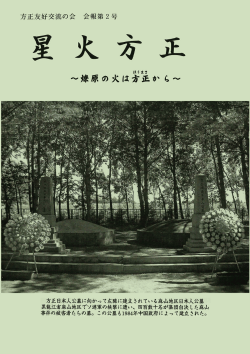中国に存在する『日本人公墓』を知ってますか?

中国ハルピン市郊外の方正県に、5000人近い死者たちを葬る『日本人公墓』が存在しています。日本の敗戦の混乱により、旧満州に置き去りにされ、亡くなった人たちのお墓です。
もともと中国の土地であった旧満州に国策として入り込んだ開拓民は、1945年の夏、ソ連軍の旧満州への侵攻、それに続く敗戦の知らせと同時に祖国を目指して逃げ惑い、難民、流浪の民と化しました。人々は、零下40度という厳冬の酷寒にさらされ、飢えと栄養失調、発疹チフスなどによってこの方正の地で息絶えました。
方正県に行けば、関東軍(日本軍)がいる。そこには軍の物資補給基地がある。人々は、方正県に行けばハルピンに行ける。ハルピンまで行けば日本に帰れると思い、必死の思いで方正にたどり着きました。しかし結果は悲惨なものでした。関東軍はすでに人々を置き去りにし、逃げ出した後でした。無念の思いを抱き亡くなった日本人たちの遺体は、各収容所で山積みになりました。しかし、暖かい春を迎えると、凍った遺体も溶け出します。方正県政府は、人と車を動員し、遺体を集め、3日3晩石油をかけて焼きました。
 1963年の春、食糧危機に陥った中国政府は、荒地を開墾して畑にし、自分たちで食糧を求めるよう命令を発しました。中国人と結婚した残留婦人・松田ちゑさんは、その荒地を探す中で、累々たる白骨の山を見つけました。それは、1945年の秋から翌年にかけて亡くなった日本人たちの遺骨だったのです。松田さんは、なんとかして骨を拾い埋葬したいと県政府に願い出ました。その願いは県政府から省政府へ、そして中央政府へ、当時の外交部長である陳毅氏を経て、最終的には周恩来首相のもとまで届き、日本人公墓の建立が許可されました。
1963年の春、食糧危機に陥った中国政府は、荒地を開墾して畑にし、自分たちで食糧を求めるよう命令を発しました。中国人と結婚した残留婦人・松田ちゑさんは、その荒地を探す中で、累々たる白骨の山を見つけました。それは、1945年の秋から翌年にかけて亡くなった日本人たちの遺骨だったのです。松田さんは、なんとかして骨を拾い埋葬したいと県政府に願い出ました。その願いは県政府から省政府へ、そして中央政府へ、当時の外交部長である陳毅氏を経て、最終的には周恩来首相のもとまで届き、日本人公墓の建立が許可されました。
1963年5月、県政府から松田さんに呼び出しがあり、こう伝えました。「あなたたちの願いはよくわかりました。あなたたちも日本軍国主義の犠牲者です。皆さんは現在中国の社会主義建設のために積極的に努力してくださっている。墓碑の建立は人民政府の手でやることに決まりました。皆さんは安心して家で一生懸命働いてください」
松田さんは、感謝の気持ちでいっぱいです。どうお礼の言葉を述べていいかわかりません。何度も「人民政府の皆さん、ありがとうございます、ありがとうございます」と頭を下げました。中国ではまだ日本の侵略に対する恨みが衰えていない1963年、日中が国交を回復する10年ほど前のことです。
黒竜江省政府は、ハルピン市の朽ち果てた外人墓地の、所有者がわからない膨大な墓石の中から、一番大きく一番きれいなイタリア製の花崗岩を探し出してくれました。優れた書家に「方正地区日本人公墓」という碑銘を刻んでもらった高さ3.3mの石碑は、2日がかりで、ハルピンから方正県まで運ばれました。まだ貧しかった中国ですが、それでも大金を投じて日本人公墓を建立してくれたのです。66年から荒れ狂った文化大革命の時、紅衛兵たちがこの日本人公墓を破壊しようとしました。しかし省政府は、「これは日本軍の墓ではない。日本の庶民の墓である。彼らに罪はない」と紅衛兵の要求を退けました。
中国政府及び中国の人々は、民族の憎悪を乗り越えて、日本人公墓を建立してくれたのです。中国で唯一、建立を許されたこの日本人公墓こそ、日中のいかなる時代にあっても、友好の思いを回帰させるにふさわしい象徴的なものであると私たちは考えます。
ナショナリズムを超える国際的な友愛精神から生まれた日本人公墓の存在は、今後の日中関係だけでなく世界のありようを考える時、ますます大きな意味を私たちに教えるものだと思います。
なぜ方正(ほうまさ)なのか? なぜ『星火方正』(せいかほうまさ)なのか?
方正と書けば日本人なら「ほうせい」と呼ぶのが普通でしょう。しかし黒龍江省には宝清という県があり、旧満洲にいた日本人たちは、「ほうせい」と呼ぶ場合は宝清を指しました。その宝清と区別するために、方正を音訓混じりで敢えて、「ほうまさ」と呼び、今でもそう読んでいます。戦後も彼の地で過ごした人々にとって方正はあくまでも「ほうまさ」なのです。私たちも彼らの思いを受けて、会の名称を「方正友好交流の会」としました。
また、星火とは、とても小さな火のことでです。私たちの活動も今は小さな野火にすぎませんが、やがて「燎原の火のように方正から平和と人類愛的な友愛の精神が広まるのだ」という意味を込めて会報の名前にしました。
方正日本人公墓が私たちに問いかけるものとは…
私たちの会報『星火方正(年2回刊行)』には、「公墓」に関する日中関係者らの声が凝縮されています。
|